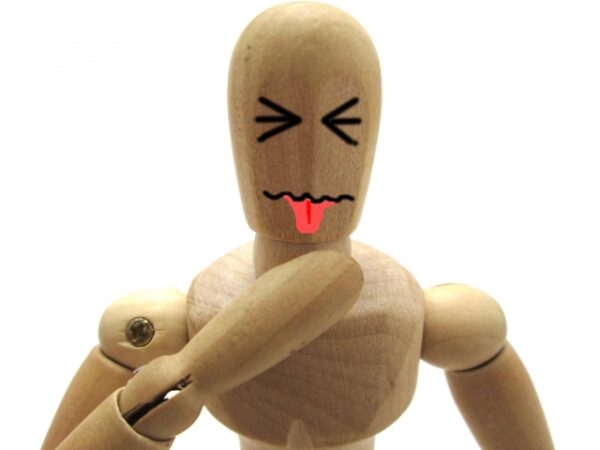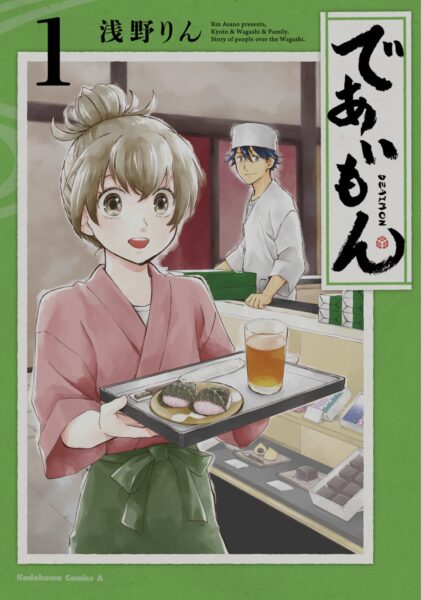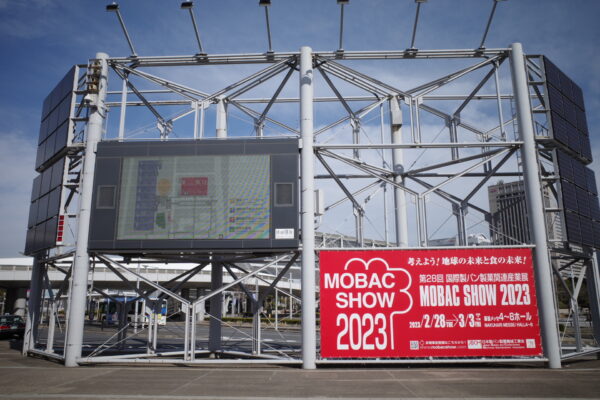1か月程前にChatGPTに「あん庵」の事を聞いたら知らないという事だったんですね。1か月ぶりにもう一度聞いてみたら何と!次のように変わってました。
ChatGPT返信①—————
和菓子工房あん庵は、大阪市中央区にある老舗の和菓子店です。創業は明治時代の1885年で、現在は5代目の当主が経営を担っています。
あん庵の代表的な商品としては、「練り切り」と呼ばれる柔らかく口どけの良い羊羹があります。また、大阪名物の「どて焼き」と呼ばれる焼き菓子も有名です。この他にも、季節限定の和菓子や、贈答用の商品なども充実しています。
和菓子工房あん庵では、和菓子作りの体験教室も開催されています。予約が必要ですが、初心者でも参加しやすいように、基本的な道具や材料などは用意されています。和菓子作りの楽しみを体験してみたい方にはおすすめの施設です。

———————————————————————–
1885年創業で5代目らしいです(僕は初代です…)煉りきりが羊羹だったり、どて焼き(どら焼きの間違い?)が和菓子だったりと違う所も多いのですが、以前は「知らない」と言われてたんですよ。それが認識されるようになったってすごい事だと思います!
あと何か月か経てば正確になるんじゃないかも知れませんね。
そして次の文章はGoogle Chrome の拡張機能でChatGPT for Google から貼りつけたものです。Google で検索をかけるとリアルタイムでChatGPTでの答えが検索結果に表示されるというものです。どういう訳か少し答えが違うんですね。
というか、MicrosoftのChatGPTに対抗してGoogle はBardを出すと思ってたのですが、まだリリースされないのでしょうか?知らないうちにchromeにChatGPTの拡張機能がついてたのでびっくりしました。あきらめたのかな?
当然MicrosoftのedgeではBingを利用してChatGPTの拡張機能は使えるみたいですが、こちらはまだ試してません
話が横にそれましたが、以下の文章です。あん庵は豊中市ではなくて羽曳野市なんですが大分近づいてきました。頑張れ!
ChatGPT返信②————————————
和菓子工房あん庵は、大阪府豊中市にある和菓子店です。伝統的な和菓子のほか、季節限定の商品やオリジナルの菓子も取り扱っています。
あん庵の特徴は、素材にこだわった手作りの和菓子を提供していることです。店舗で使用する素材は、全て国内産のものを使用しており、化学調味料や合成着色料は使用していません。また、店内には職人が常駐しており、一つ一つ丁寧に手作りされた和菓子を味わうことができます。
あん庵の代表的な商品には、「どら焼き」「羊羹」「生チョコ餅」などがあります。どら焼きは、もちもちとした皮と、なめらかなこし餡が絶妙なバランスで調和している人気商品です。羊羹は、上品な甘さともちもちとした食感が特徴的で、季節限定のフルーツを使ったバリエーションも豊富です。また、生チョコ餅は、しっとりとした餅生地と、濃厚な生チョコレートが絶妙な味わいの商品です。
店舗では、和菓子のほかにも、お茶やコーヒーなどのドリンク類も取り扱っており、店内で和菓子と一緒に楽しむことができます。また、オンラインショップもあり、全国に発送しているため、遠方にお住まいの方でも手軽にあん庵

—————————————————————————–
文章が途中で止まってる感はあるもののまあいいか。
そしてchromeの拡張機能でもう一つ。「インターネットにアクセスできる ChatGPT」を使ってみます。ご存知の方も多いと思うのですが、 ChatGPTは今のところインターネットをリアルに解析して答えを導くものではないので、情報が若干古いという欠点はあります。それでも進化していくのですからどうなってるんだと驚くばかりですが。
そんな欠点を補うためにネット情報を補足しながら答えを導く拡張機能がその「インターネットにアクセスできる ChatGPT」です。どう変わっていくのでしょうか?
ChatGPT返信③————————————-
提供された Web 検索結果によると、「和菓子工房あん庵」は日本の大阪に複数の店舗を持つ和菓子店のようです。北海道産の無農薬小豆など、上質な素材を使ったあんこや餅などの伝統的な和菓子を提供しています。店内にはドリンクやスイーツを提供するカフェも併設。Web サイトでは、連絡先情報と製品を購入するためのオンライン ストアを提供しています。
和菓子屋「和菓子工房あん庵」の検索結果です。検索結果には、ショップの Web サイト、オンライン ショップ、および日本の大阪にある 2 つの実店舗へのリンクが含まれています。ホームページには、お店の商品や素材、製法などの情報が掲載されています。実店舗では伝統的な和菓子と、ドリンクや軽食を提供するカフェを提供しています。ウェブサイトでは、2 つの実店舗へのアクセス情報も提供しています。

————————————————————————————-
おお!ほぼほぼ正確に情報が出てきました!
素晴らしい!
インターネットが出てきて「検索」という概念が出来て20数年。今では当たり前のことになってるのが大きく変わるかも知れませんね。令和生まれの子が大きくなったらGoogleよりもAIに聞くのが当たり前になっていて「えっ!昔はわざわざ検索ってことをしていたの?」って驚かれる日が来るかもしれません。
時代に取り残されないようにしないと・・・