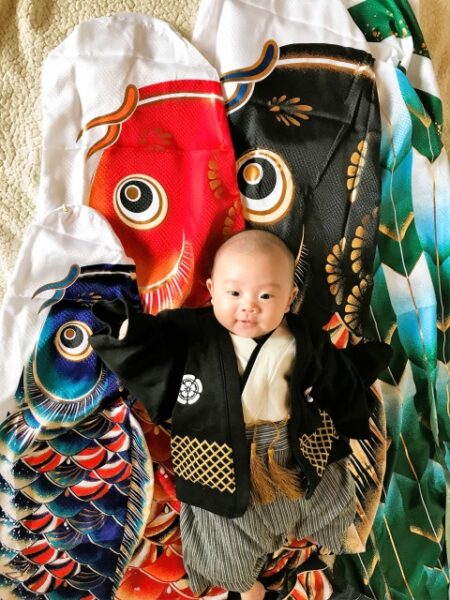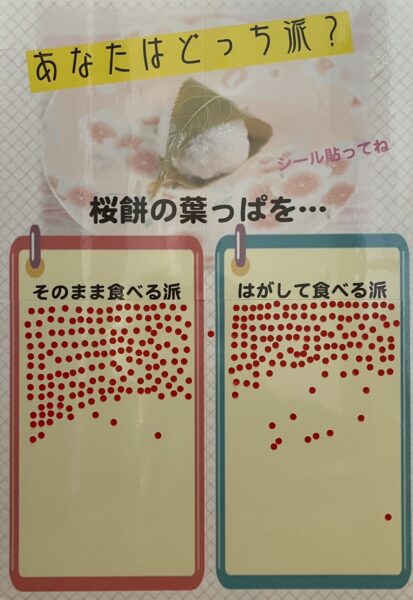●春告鳥●
小さい時は、ツバメが家に来てくれないかなぁってすごく思ってました。ツバメの頃家は幸せが訪れるとも聞いたことがあります。でも実際来たらフンの始末とか大変そう(笑)
ツバメは春になったら現れる渡り鳥なので別名「春告鳥」って呼ばれたりします。和菓子の世界?で「春告鳥」って言われたらやっぱり「うぐいす」を連想するというか、実際に菓名になったりしてます。まぁ両方とも間違いでは無いですよね。

●なぜ軒下に●
ツバメが人の軒先に巣を作るのはカラスなどの外敵から卵やヒナを守るためだということは結構知られていますよね。人はカラスや蛇などは除外しますが、ツバメには危害を加えない。そんなことを知っているツバメって偉いですね。かつては昔の人は雀や鳩も食してたと思うのですが、そういえばツバメって食べませんし、どちらかというと微笑ましくて守ってしまいますよね。

●ツバメの子育て●
さて、ツバメの卵が孵化するのは産卵から2週間。雛が巣立つのは3週間。1日一羽につき100匹ほどの虫を食べるそうですから、子育てホンマ大変です。
育ったら今度は人家から離れて自然の中に寝ぐらを作って集団で過ごします。 そう、成人?すると軒先の巣から山などへと引っ越しする訳なんです。
でも、長めにみても産卵から巣立ちまでは2ヶ月くらいですよね。渡り鳥なんで半年近くはいるはずなんですが・・・。
そう、子育ては1回じゃ無いんです。大体のツバメは2回卵を産んで子育てします。
そして秋には東南アジアの方に渡っていきます。春にはまた日本に戻ってきます。

●越冬つばめ●
ヒュ~ルリ~~~ヒュルリララ~~~
小学生の時に好きな芸能人と聞かれて森昌子と言ってだいぶ引かれたのを思い出します。
「越冬つばめ」聞きたい方は下をクリック!
https://youtu.be/bTUuzOu5iiw
という、越冬ツバメなんですが、普通に九州ではよく見るそうです。この歌のイメージは九州よりもなんか雪国の感じがしますが、実際は暖かいところにいる様ですね。
でも不思議に思いません?

日本では越冬出来ないので東南アジアに渡るんですが、東南アジアって1年中暖かいんです。
だったらわざわざ命の危険をおかして日本まで来なくても東南アジアで年中暮らすっていうライフスタイルでも良かったんでは無いかと。
実は東南アジアはそこまで大量に虫がいるわけでもなく、また他の鳥とも取り合いになるので雛を育てるには爆発的に虫が増える日本の春夏が適してるそうです。
だからツバメにしたら子育ては日本でして冬は寒いから暖かいところに避難するみたいな感じで、ベースはどうも日本のようですね。
●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
——————————————————————————————————
七十二候という季節があります。恐らく世界で日本だけだと思います。四季が明確にあるだけでも珍しいのに、それをさらに24もの季節に分けた皆様ご存知の「二十四節気」という季節があります。いわゆる「立春」とか「夏至」とか「大寒」とかですね。その24の季節を更に各3つの季節に分けたものが「七十二候」と呼ばれる季節です。
おおよそ5日ほどで変わっていく季節。そんなに変化ある?って思う方もおられると思いますが、季節の名前を聞くと「なるほど!」ってうなづける事も多いです。日本の素晴らしい環境とそれを感じとる感性豊かな日本人。日本に生まれてきて良かったと感じる瞬間です。
(元々この暦も中国から入って来たとされてますが、現代に残ってる暦は日本に合わせて日本独自にブラッシュアップされたものと言えます)
参考文献
日本の七十二候を楽しむ~旧暦のある暮らし~
白井明大(株KADOKAWA)
季節七十二で候。
大田垣晴子(株KADOKAWA)
くらしのこよみ
うつくしいくらしかた研究所
くらしを楽しむ七十二候
広田千悦子(泰文堂)
にっぽんの七十二候
角謙二(株式会社枻出版社)
——————————————————————————————————