
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

デフリンピックってご存知でしょうか?
1924年にパリで第1回大会が開かれ、2025年は東京で開催します。(因みにパラリンピックは1960年からなので歴史はデフリンピックの方が長い)
ほとんどの方がご存知ないかも知れません。僕も恥ずかしながら今日知ったのですが、「デフ」とは英語で「聞こえない」という意味で、耳が聞こえない、聞こえにくい人の為のオリンピックとなり、選手は補聴器無しで競技をすることになります。
その中でデフサッカーの日本代表の選手達の講演を聞きにきました。生い立ちから、苦労した事、希望を持った事など色んな話を赤裸々に語ってくれました。色々学べました
ご興味ある方はクラウドファンディングもされているので、ぜひご協力を
https://camp-fire.jp/projects/823282/view
●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E
1年で1番お餅が売れる時はやっぱりお正月なのですが、実は年間通して結構コンスタントにご注文いただきます
お祝い事や法事で使われるためのお餅も多いのですが、純粋に普段食べるようでご注文いただいたりもします。(朝ごはんが多いかな)
関西では丸餅が一般的なのですが、写真のような棒餅をカットしてねってご注文いただくこともあります。
因みにウチの地域は「棒餅」を「ねこ」「ねこ餅」と言ったり「のし餅」と言ったりします。
そのお餅の中でも、うるち米(もち米じゃなくて普段食べるお米の事)を混ぜ込んだ「うるう餅/うる餅」がお餅マニア?の間では人気です
食感が良いんですよね
そして、さらにお正月のメニューに無い裏メニューの「黒ゴマ味」は黒ごまペーストと黒ゴマをふんだんに練り込んだうるう餅のねこなのです。奥深いにゃ〜
#お餅 #ねこ #ねこ餅 #のし餅 #うる餅 #よもぎ #桜えび #黒豆 #黒ごま #お餅は朝ごはん

 今日はシュークリームの日❣
今日はシュークリームの日❣
毎月1日なのですが、節分と重なったため、今月は8日になりましたm(__)m
美味しいシュークリームが食べたくて20年ほど前に自分で作ったのがきっかけです。和菓子屋らしく葛でカスタード炊いたり。
因みにカスタードクリームは英語で、本場フランスだとクレーム・パティシエールって言う名前です。パティシエールって言うのは菓子職人を表すパティシエの女性形の事ですが、広い意味でお菓子屋さんのクリームっていう解釈が出来るようです。
どちらにせよお菓子の基本になる代表的なクリームってことなんですね。和菓子屋で言うとあんこみたいなものですかね~(^^♪



初釜にお呼ばれ致しまして行ってきました。
早朝はあいにくの雨模様だったので、先日岐阜で買った蛇の目傘の登場だ!と思い張り切って出したのですが、この写真の通り出かける寸前には晴れ間がのぞく様になりました。折角なので写真だけ撮っときました。
初釜自体は毎年の事ですが非常に心洗われる感じで、新年を満喫いたしました。
今年1年よろしくお願いいたします。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E

インテックス大阪で富田林市からフードストアソリューションズフェアに出展しました。
あん庵は元々富田林市の喜志という町からスタートしました。そして数年後に隣の羽曳野市に工房を移設し、法人化をしたこともあって羽曳が丘を本店としたのですが、もちろん思い入れはどちらの市にもあります。生まれ育ったのは羽曳野市ですが、高校は富田林市ですし。

まぁそれはおいといて、今日はいろんな方との出会いがあり楽しかったです。
もちろん仕事の話がほとんどですけど、それ自体が楽しいんですよね
ご縁に感謝です。


●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E
営業時間を変更しました。
少し短くなってしまいお客様にはご不便をおかけします。
だったら短くしなければいいのにねって声が聞こえてきますね。
すみません。。。
この店をオープンしたのは22年前。色んな人に支えられて手伝ってもらったので、決して一人でしてた訳じゃないんですが、毎日のルーティーンは言ってもやはり一人で作ってました。
なので1日20時間位働いてまして、毎日もう死ぬって思いながらしてましたが、案外身体が丈夫で倒れたりもしなかったですね。あ、1回倒れたわ。2回かな?
でもね、ありがたいことに社員も入ってきてくれてパートさん、アルバイトさんも述べ200人は軽く超えるほど働いてくれました。
特徴的な子も多かったので覚えてる子も多いし、今も付き合いのある子も何人もいます。ま、とにかく僕も歳取りましたし現代の働き方に合わせて店の営業時間を減らしました。来年はもっと減るかもしれません。
ただ、単純に時間が減るだけではお客様に迷惑をおかけするだけなので、余力を面白い方向に使っていこうかなと思ってます〜
今年の桜はやや咲くのが遅かったかな?
入学式には散り始めていた年もあったのに僕の地域では4/1の時点でまだ3部咲き程度ですね。
桜WEEKとしまして地元の四天王寺大学さんが一般の方にキャンパスを開放しました。3部咲きとはいえ広大なキャンパスに咲く桜は綺麗ですし、正門からの桜のトンネルは圧巻です。あと三日くらいで急速に満開になると思います。
あん庵も3日間お菓子を販売させて頂きました。入学式もありお赤飯も速攻で売り切れてしまいました
新入生、初々しかったですね((o(>▽<)o))


●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E







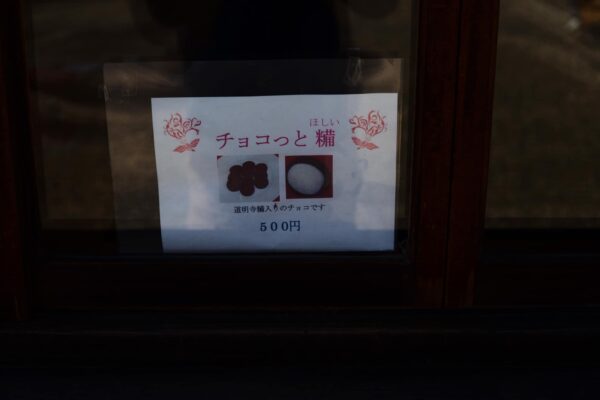











年末年始ほったらかしだった母を初詣兼ねてえべっさんに連れて行きました
「え〜、久々に来たけど、風景が変わってしもてる」
「そうなん?」
「こんな高いビルは無かったわ」
「最近増えたんかいなぁ」
「道もこんなアスファルトじやゃなかったで」
「・・・・・何年振りなん?」
「60年ぶりくらいかなぁ」
「そら、変わってるやろな・・・・」
なんて会話をしながら、お参りを済ませ、昼ごはんを「大阪球場の跡地」である(笑)「なんばパークス」で食べようと連れて行き、
「何食べたい?」
と聞いたら「ここにする」って
まさかの人生初のインド料理をチョイスしました
出不精なのに好奇心はある母でした
●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E
元日 20:50よりフジテレビ(8ch)で有吉弘行さんの番組
✧✧ 有吉弘行の爆食ツアー!芸能人の勝負差し入れフェス ✧✧
の中で「大阪ええYOKAN」が紹介されました。
そのシリーズの中でも一番高級な「秀吉の茶室かん」という羊羹が9個入った「豪華絢爛セット」(定価が何と19,764円!)をスノーマンの宮舘君が20箱もお買上げくださったのです。
※「大阪ええYOKAN」とは、高山堂さんが呼びかけて大阪の和洋菓子店(約10店舗)+大阪緑涼高校が企画・参加するプロジェクトで2023年5月にデビューしました。梅田の大丸百貨店、阪急百貨店を中心に催事を行っています。
今年の春節ではなんと海を越え、台湾にも上陸いたします。
あん庵では通販サイトや店頭でも常時販売してます!
—以下番組ロケに行った裏話—
この番組は有吉さん、吉村さん(平成ノブシコブシ)、みちょぱさん、田中さん(アンガールズ)が全国をプライベートジェットで巡るという番組です。関西地区では他にもふわちゃん、ハラミちゃん、そしてスノーマンの宮舘くん、深澤くん、佐久間くんが合流してくれたのです。
その有吉さん御一行が到着するのは15:00とか16:00の予定なのですが、現地入りはなんと9:00でした。まぁ準備が大変ですからそれくらいは時間がかかるのは当然ですよね。
場所は神戸メリケンパークのオリエンタルホテル。いいホテルですね。近くすぎて一生泊まることはないかもしれないですね。
そしてリハーサルも念入りにしました。スタッフがそれぞれ出演者を演じて各ブースを回るのです。12ブースがあり、本番と同じくらい時間をかけて回ります。スタッフの会話を聞いてると本当にタレントさんの良いそうなセリフや、ボケ・ツッコミをしてて、それ見てるだけでも面白かったです。
ですが、いくら特徴をとらえてうまく喋ってたとはいえ、あくまで想像上ですから実際はどうだったかというと、リハーサルで会話したこととは全く違うかったので、さっきのリハの意味は〜っていうよりかは、もう笑ってしまいました。でもそれが逆にリアリティありましたよね。
他の店も魅力的なお店がずらりと並んでいて、牛タン煮込みの店とかどんだけいい匂いするねんって感じで、食べたいのに食べれないフラストレーションが溜まりました(笑) 少しは待ち時間に話せたので隣の和菓子屋さんとも仲が良くなったり、面白かったです。
さてさて、有吉さん御一行が到着したと一報が入り、本番前に一番最初に入ってきたのは有吉さん!ではなくて進行役の吉村さんでした。その眼光の鋭さと状況判断、仕切る能力が秀逸。画面に映らない一面を見たような気がしました。
有吉さん、もうなんか貫禄あって猿岩石の時代(古い!)より当たり前ですが、大御所感が凄かったです。田中さんはなんか優しそうな感じでしたねぇ。みちょぱさんはやっぱり綺麗でしたし。そう言えばじゃんけんで負けて140万円を払うことになりましたが、いくら何でも本当に払わすのか?って思ってたんです。でもカメラの回ってないところでも結構悔しがってたので、本当に払ってそうです。芸能界怖い。
はらみちゃんはピアノが得意というか本職なんですよね。本当に芸能界に疎いので全然分からずです。
ふわちゃんはちゃんと見たことはなかったのですが、さすがに目立ってるので何となくは知ってました。
さてそしてスノーマンの登場です。本当ファンの方に聞かれたら怒られそうなんですけど、TVも疎いのですが、アイドルにはもっと疎く、全然知らなかったんです。すみません。。。
深澤くん、宮舘くん、佐久間くんが参加してくれて、12件ある名店を回っていってます。ウチは最後の方だったので成り行きを見ながら待ってました。そしてついにあん庵の番です。
9人の芸能人が一斉に話すのはもう圧巻で迫力満点です。
そんな中、スノーマンの宮舘くんが現在出演してるフジテレビの「大奥」のスタッフや出演者に持って行きたいということで、全面金箔の「秀吉の茶室かん」が9個入った「豪華絢爛セット」を・・・値段を聞かずに20箱!購入して頂けたのです。何という買いっぷりなのでしょう。人気があるのもうなづけます。
値段を聞いて、一瞬びっくりしてましたが、揺るぎなく押し切りました!すごいですね。
その後の支払いをかけてのじゃんけんにも勝つというところがやはり持ってます!
そして実はその後、カメラが回ってない時に深澤くんが店に来てくれて、こそっと?この豪華絢爛セットを購入頂きました。宮舘くんも男気がありましたが、深澤くんも何とも爽やかな空気感がありました。
そう言えば何年か前にジャニーズWESTの中間淳太くんがウチの店に一日修行しに来てくれた時に感じた爽やかさと似通ってるものがある感じでした。あの時は本当に1日仕事してくれたので、昼ごはんとかも一緒にわいわい話しながら食べたりして楽しかったです。
まぁそんなこんなで長かった1日が終わり、折角やからオリエンタルホテルで晩御飯食べて帰りました!
皆様お疲れ様でした((o(>▽<)o))
●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E
令和6年能登半島地震の被災者の方にはお見舞い申し上げます。
和菓子屋の知り合いもいるので心配しましたが、みんな無事のようで何よりでした。
もっとも、和菓子関係者以外でたくさんの方がお亡くなりになったり、お怪我をされています。一刻も早い救助を願います。僕も大したことは出来ませんが少しでもお役に立てることをしたいと思います。
南海トラフ地震は終戦から間もない昭和21年に起こり、ウチの親父も体験談をよく語ってました。100年程度の頻度で起こるようなので、いつ起こっても不思議ではありません。日本の地形を見てみても安全な地域はないかも知れませんね。
出来ることといえばささやかな自己防衛と、起きてしまった地域の方への支援ですかね。出来れば誰しもが平和で穏便に暮らしたいものです。

●松田なんで店をつくったのか? https://w-anan.jp/about/
●お菓子作り紹介(和菓子職人あきらYoutubeチャンネル) https://youtu.be/Ol1nHE2v00E